ことばの発達
人間にとって「言葉」とは
情報伝達の信号としての「言葉」であれば、ミツバチやイルカなど人間以外の動物にも扱うことができます。
しかし、人間にとっての「言葉」は単なる信号ではなく、概念や規範としての役割をもちます。
また、同時に相互交流のチャンネルでもあり、言葉によって体験を共有し合ったり、関係を持ちあったりしています。
例えば、「今日は天気が悪いです」と言うと、天候に対するひとつの認識を表すだけの言葉です。

それに対して、「今日は天気が悪いですね」と言うと、天候への認識だけでなく、その認識を相手と分かち合おうとする話し手の気持ち(情動)が加えられています。
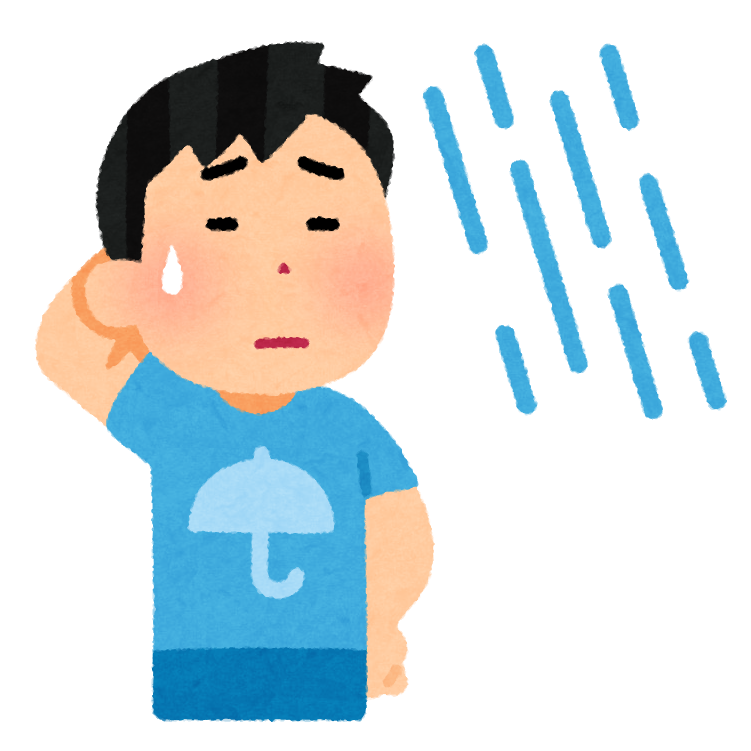
言葉の発達
そもそも言葉はどのようにして発達していくのでしょうか。
言語のはじまりは「指さし」といわれています。
1歳半健診で指さしができるかどうかがひとつの基準となっているのはそのためです。
目安として8~10ヶ月を過ぎると指さしができるようになります。
指をさすという行為は、相手への伝達を意図した明らかな表現です。
それまでの子どもは「自分と他者」や「自分と対象物」という2つの関係しか存在していませんでした。
しかし、指さしをするようになった子どもは「指をさす-さされた対象-それを見る人」という三項関係を認識できるようになったということです。
これがコミュニケーションには非常に重要です。
なぜなら、コミュニケーションは「話し手-話の内容-聞き手」という三項関係と同じ型をとるからです。

一語文
指さしができるようになったら、次は単語です。
これが「一語文」と呼ばれるもので、「話し始め」ともいいます。
最初は「マンマ」「ワンワン」「ブーブー」など直接見たり触ったりする実体的な物の呼び名から始まります。
単にいろいろな物の名前を記憶すればいいような気もしますが、それほど簡単なことではありません。
例えば犬を見て「ワンワン」というとき。
犬は大きい犬から小さい犬、毛がふわふわの犬、真っ黒な犬などさまざまですね。
そのどれを見ても「ワンワン」といえるのはなぜでしょうか?
それは「抽象能力」という力が影響しています。
形や色はさまざまですが、足が4本生えていて、毛がふわふわ生えている動物のことを「犬」と認識します。
もちろんすぐにできるようになるわけではありません。
猫を見て「ワンワン」と言ったり、動物園でクマを見て「ワンワン」と言ったりします。
その度に、養育者が「あれはクマだよ」「あれはワンワンだね」などと言って相互交流しながら、少しずつ子どもたちは言葉を身につけていくのです💡
二語文
一語文が言えるようになったら、次は二語文です。
これは、「単語」から「文」にステップアップしたことを意味しています。
例えば「クック ナイナイ」という二語文は、
表現されていないだけで「クック(ヲ)ナイナイ」と言っているのです。
これはつまり、動詞や形容詞をつなぐ助詞の役割をもちます。
発達はステップアップ
このように、言葉の発達は少しずつステップアップを踏んでいきます。
言葉に限らず、発達というものは段階を踏んでできることが増えていきます。
「苦手かな?」「ゆっくりかな?」と感じた場合は、どの段階でつまずいているのかを探ることがとても大切です。
一言で「言葉がゆっくり」といっても、その要因や状態はさまざまです。
もしお困りのことがありましたら、当院までお気軽にご相談ください😊✨
