クリニック新聞7月号「診断されたら”こころ”が病んでいるということ?」
こんにちは😀
8月は夏休みの時期ですね🍉
疲れた体を休めて、リフレッシュする時間が過ごせますように🌟
さて、先月号のクリニック新聞のテーマは「診断されたら”こころ”が病んでいるということ?」でした!
思春期外来を受診した子どもたちの中には、さまざまな「こころの病気」の診断がつくことがあります。
当院でも多くのお子さまが通院されています。
「診断」は、今後の治療方針を決めたり、現在の困りごとを理解したりするために大切なことです。
ただ、ここで注意したいのは「彼らのこころの全てが病んでいるわけではない」ということです!
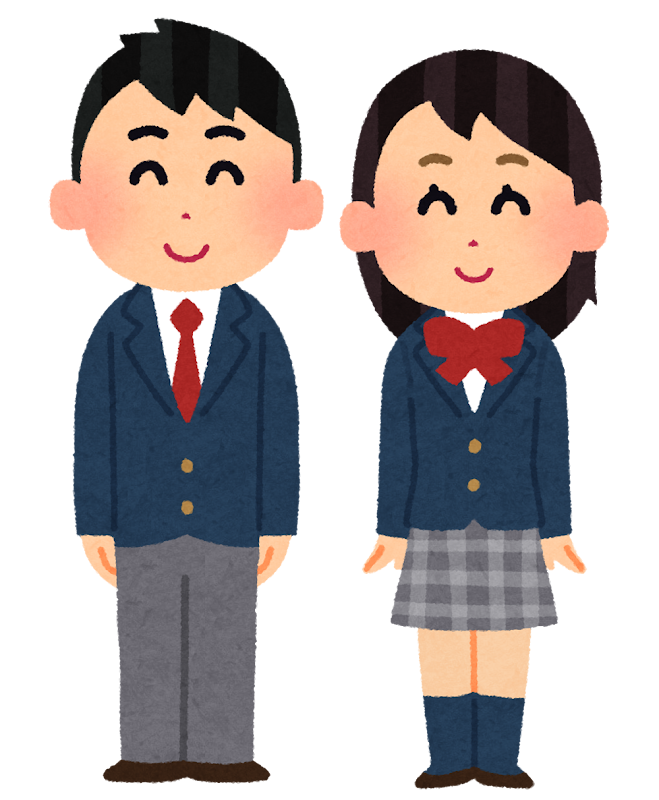
子どもたちは、確かに病気の部分があるかもしれませんが、それはごく一部で、残りの多くの部分は健康なままです。
それなのに、大人が「この子は〇〇病」「△△障害の子」というレッテルを貼ってしまうと、その子の健康的な部分が見えづらくなってしまいます。
人のこころはシンプルなつくりではなく複雑です。いろんな側面があって当然なのです。
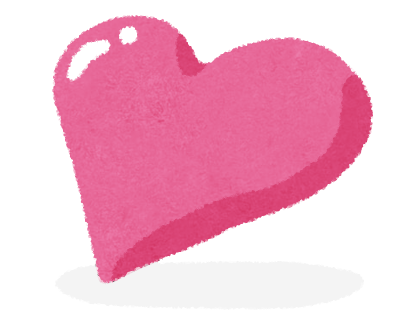
そして、その「健康的な部分」に注目することが治療には必要です💡
子どもたちは診察の中で、ゲームやアニメ、音楽、動画など自分が好きなものについて話してくれることがあります。
自分の興味・関心のあることを話すうちに、いつしか症状や悩みは軽くなり、家庭や学校での生活も安定するという場合もあります。

診断を受けた子どもたちには確かに悩みごとや症状がありますが、1人の人間として生きている存在でもあります。
苦しいこともありますが、楽しいことも同じように経験しているのです。
今回は思春期の子どもたちを例に挙げましたが、子どもに限ったことではなく大人に対しても同じように考えることができると思います。
「こころの病気」という診断を受けると、こころ全てが病気であるかのように見えてしまうかもしれませんが、健康的な部分は誰にでも必ずあります。
自分が興味・関心のあることや楽しいと感じていることをじっくり聞いてもらうことで、自分が認められ、自分らしく振舞えるようになると思います。
それが子どもの場合は特に顕著です。
そうすると、こころに占める病気の部分が小さくなり、健康的な部分が大きくなりやすいです。
「できないこと」「病気」の部分に目を向けすぎると健康的な部分は見えづらくなります。
ぜひ、「できていること」「好きなこと」に目を向けることを意識してみてください♪
【引用文献】武井明(2024)思春期外来での臨床から.こころの科学,234,23-28
