思春期の子とのコミュニケーション
ご家族のみなさまへ
こんにちは😀✨
今回は思春期のお子さまをもつご家族に向けた内容です◎
お子さまとのコミュニケーションについて、お悩みではないですか?
「そっけない態度をとられる」「自分から話をしたがらない」など、コミュニケーションがスムーズにいかない場合があるかもしれません。
一方で、成績や進路、将来のことなど保護者の方にとっては心配ごとが多い時期ですよね。
どうすれば会話をしてくれるようになるのか、どんなふうにコミュニケーションをとったらよいのか、ということについて触れていきたいと思います😊
「話をさせよう」としないこと
確かに幼児期や小学校の頃に比べて、思春期は成績や進路のことなど大事な話をしなければいけないタイミングが多いものです。
ただ、そういうことだけ話そうとしても上手くいかないことがほとんどです。
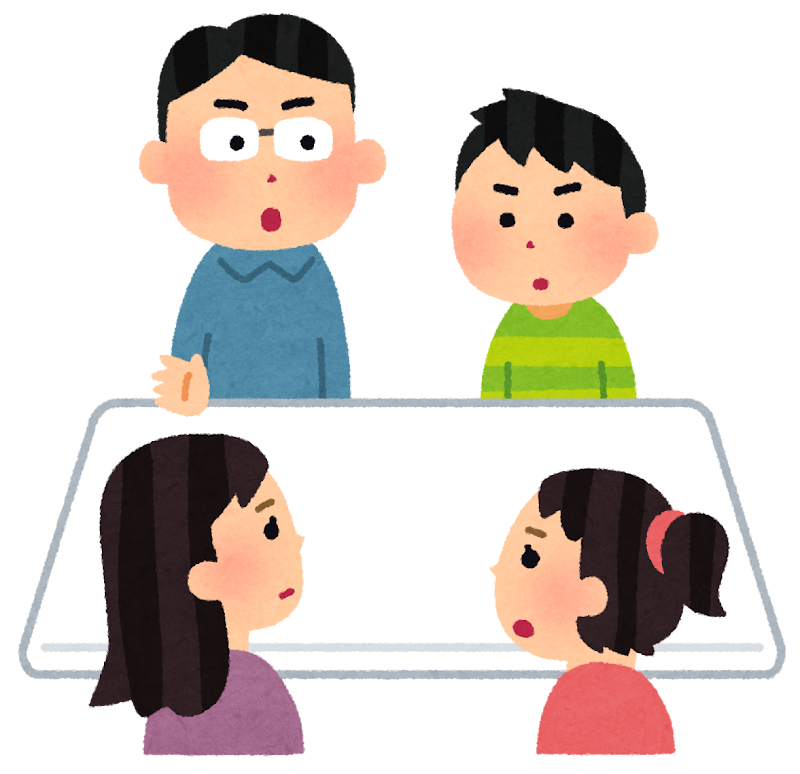
なぜなら、子どもたちはそういう話をしたら学校に行かされるのではないか、ゲームを取り上げられるのではないか、勉強しろと怒られるのではないか…など敏感に察知しているからです。

そのため、そういう話題を出したい気持ちをグッとこらえて、「何でもない会話」を心がけてみてください💡
「今日の夜ご飯なにがいい?」「このTV一緒に見ない?」など、何気ない日常会話こそ意味があります。
このときのポイントは、本人にとっても家族にとっても楽しい時間を過ごすことです。

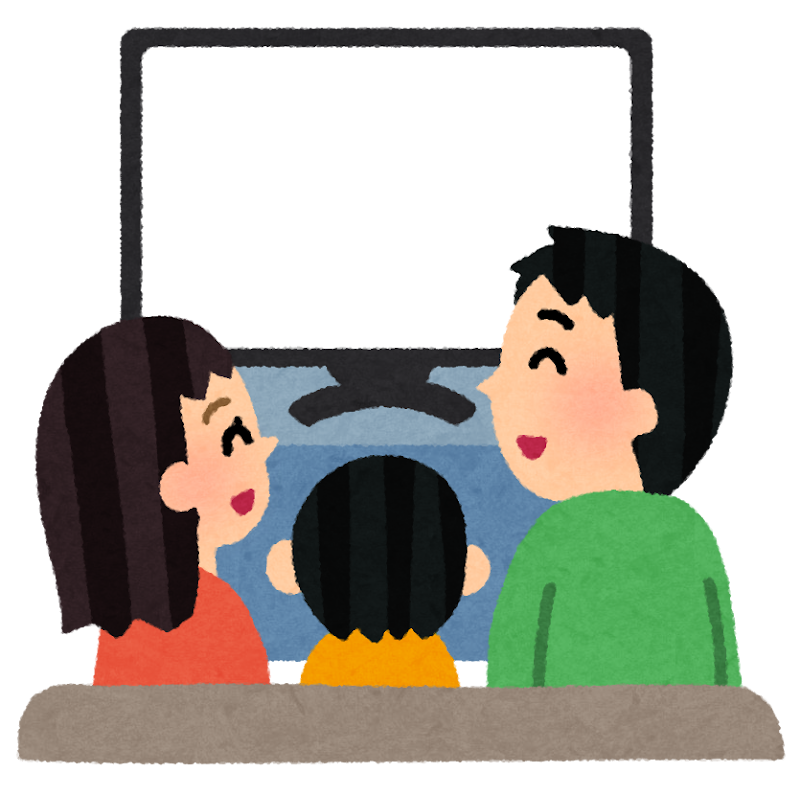
「話を聞き出してやろう」「この話が終わったら勉強の話をしてやろう」などという姿勢では絶対に聞かないでください。
遠回りのように見えますが、この「何でもない会話」を家族みんなで楽しめることで、子どもは「話しても否定されないんだ」と感じることができます。
深刻さや重要度が高いほど、「もし否定されたらどうしよう」「聞いてもらえなかったらどうしよう」と思うものです。
普段の会話の中で、「きっとどんな話をしても聞いてもらえる」「受け入れてもらえる」と思えれば、成績や進路など重要な話題も扱うことができるようになるはずです。
会話がむずかしければ
なかには関係が悪化して、「どんな話題であっても話しかけても無視されてしまう」「反抗的な態度で話しかけることすら難しい」というご家族がいるかもしれません。
そのときは、無理に話しかけようとせず、別の方法を試してみましょう😊
特におすすめしたいのは、挨拶を必ずすることです。
初めは家族の方から挨拶をしていたけれど、「どうせ無視されるから」という理由でだんだんしなくなったという方が時々いますか、これは逆効果です。
なぜなら、「挨拶をしない」ということは、そこにいるのにその存在を無視しているのと同じことだからです。
例え返事が返ってこなくても「おはよう」「おかえり」などの家族の言葉は、子どもたちはちゃんと聞いています。
この挨拶には、「あなたの存在を気にかけているよ」「あなたがそこにいることを分かっているよ」というメッセージの意味があるのです。
また、手紙を書くこともおすすめです。
手紙はリアルタイムでの会話と違い、本人のペースで読むことができます。
そのため、直接話をするよりも本人が受ける負担が少なくてすみます。
手紙の返事がくるかどうかは重要ではないので、あまりとらわれないようにしてくださいね。
手紙を書くときも、いきなり学校や進路について触れるのではなく、夜ご飯のメニューや本人が好きなことなど読んでいて嬉しい気分になる内容にしてください🌱
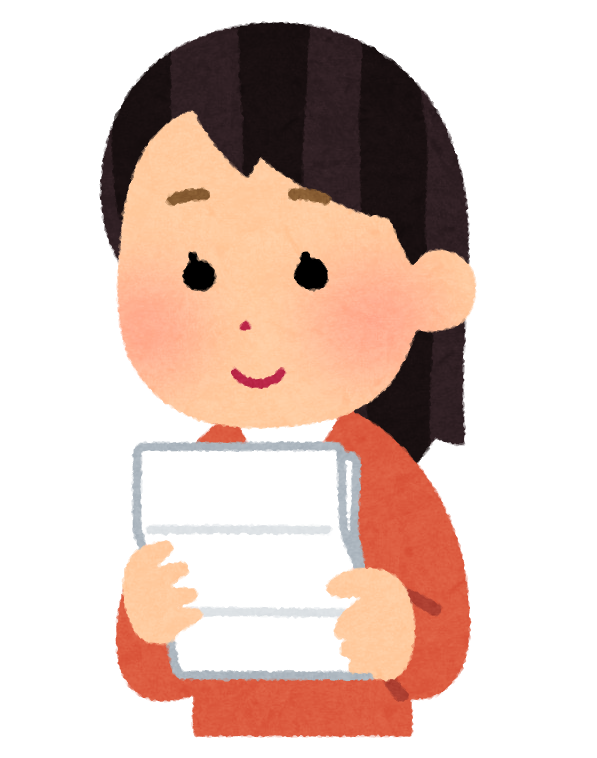
さいごに
思春期の子どもたちはとても不安定で複雑な心模様です。
それについては過去のブログで何度か触れていますので、よければそちらもご覧ください🌼
「家族にとっても本人にとっても楽しい」を合言葉に、まずは楽しくて和やかな雰囲気を目指してみてください✨
ご家庭の雰囲気が変われば、コミュニケーションの幅も広がり、よい循環ができるはずです💡
